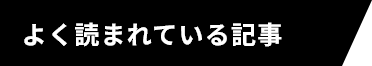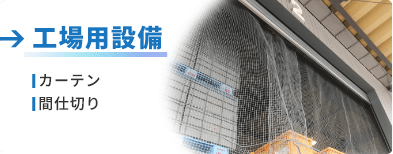広さも防水も安心!用途別に選ぶ大型テント倉庫の完全ガイド
 2025.01.20
2025.01.20
 2025.3.27
2025.3.27

「倉庫が足りない」「急な増設が必要」「コストを抑えたい」——そんな悩みを抱える企業に注目されているのがテント倉庫です。短期間で設置できるうえ、建築コストも抑えられるため、工場や物流業界をはじめ、さまざまな業種で導入が進んでいます。
さらに最近では、倉庫用途だけでなく、スポーツ施設・イベントスペース・トラックヤードとしても活用されています。本記事では、用途別の活用例や選び方、法律面のポイントまで詳しく解説します。
目次
テント倉庫の多様な用途と活用事例
テント倉庫は、保管庫としての基本的な用途に加え、物流・作業スペース、さらにはスポーツ施設やイベントスペースとしての活用も可能です。 ここでは、テント倉庫の代表的な用途と、倉庫以外の活用方法について詳しく紹介します。
テント倉庫の主な活用事例

テント倉庫は、主にモノを保管するための倉庫として利用され、以下のような業界で活用されています。
・建築機械の整備場
・電気・金属業の保管庫
・運送業の保管庫
・製造業の材料保管庫
・半製品・完成品の簡易倉庫
・食品や商品倉庫
・製品仕分け場
テント倉庫の特徴として、基礎・骨組み・テント生地のみのシンプルな構造のため、最短2~3ヶ月程度で設置が可能であり、急なスペース不足にも迅速に対応できます。 また、使用する部材が少なく済むため、コストを抑えて導入できるのも大きなメリットです。
物流・作業スペースとしての活用
大型テント倉庫は、物の保管場所としてだけでなく、荷捌き場や製品仕分け場としての利用にも適しています。天井の高さを確保することで、大型トラックやフォークリフトの出入りがスムーズになり、作業効率の向上につながります。
また、屋根付きの構造のため、雨や雪の影響を受けずに荷物を搬入・搬出できるのも大きな利点です。全天候型の作業スペースとして、安定した物流・生産活動を支えます。
テント倉庫の倉庫以外の活用事例
テント倉庫は、一定基準を満たし申請を行うことで、倉庫以外の用途でも利用できます。特に、雨風を防ぐ広いスペースを確保したいというニーズが高く、ショールームやスポーツ施設としての導入が増えています。
代表的な活用例:
・トラックの格納庫
・ショールームスペース
・ドッグランスペース
・スポーツの室内練習場
・フットサル場
・テニスコート・スケートボード場
企業ごとに、さらに多様な活用アイデアが生まれる可能性があります。
ドッグランスペース
大型テント倉庫をドッグランとして利用することで、天候に左右されない広い室内空間を確保できます。また、鉄骨構造により耐久性と安全性を確保できるため、長期的な運営にも適しています。
さらに、天井を二重張りにすることで直射日光の影響を軽減し、空調設備を導入することで一年中快適な環境を維持できます。
スポーツの室内練習場

テント倉庫を活用して、スポーツの室内練習場を設置することも可能です。
自然光を活かした設計ができるため、一般の練習場よりも照明コストを抑えられるのが特徴です。
・天井に薄いシート膜を採用し、日中は自然光を取り込み、明るいスペースを確保
・夜間は照明を併用し、ランニングコストを最小限に抑える
・広いスペースを確保し、フットサル・テニス・スケートボード場など多用途に対応
また、テント倉庫は設計の自由度が高いため、デザイン性を重視した空間作りも可能です。
テント倉庫の建築確認申請は必要か?
テント倉庫を設置する際、建築確認申請が必要なのか気になる方も多いでしょう。原則として、床面積が10㎡を超える建築物は建築確認申請が必要です。これは、簡易型のテント倉庫であっても適用されるルールです。
また、テント倉庫に関連する建築基準には、『国土交通省告示第666号』と『国土交通省告示第667号』の2種類があります。これらの違いを理解することで、用途や条件に合ったテント倉庫を選ぶことができます。
・国土交通省告示第666号:テント倉庫よりも広範な用途に対応する基準で、「膜構造物」として分類されます。倉庫以外にも、作業場・運動施設など多様な用途で使用可能です。
・国土交通省告示第667号:テント倉庫の低コスト化や納期短縮を目的とした基準。一般的に「テント倉庫」として認識される建築物はこの基準に基づいています。
やや分かりづらい部分もありますが、用途や建築基準の違いに応じて適用される基準が変わるため、導入前にしっかり確認することが重要です。 以下に、「667号」と「666号」の違いを分かりやすく表にまとめましたので、ご参考ください。
| 条件 | 国交告示667号 | 国交告示666号 |
| 対象 | テント倉庫 | 膜構造建築物全般 |
| 使用目的 | 倉庫・物品保管限定 | 倉庫・物品保管・荷捌き場・作業場・運動施設……などに利用できる |
| テント倉庫の面積 | 延べ床面積1,000㎡以下 | 特に制限はなし |
| 高さ・間口の制限 | 軒高5m以下、間口30m以下 | 最高の高さ13m以下 |
| 壁面 | 壁が必要 | 壁面オープン設計も可 |
| 評価 | 比較的安く建設可能 | 667号より自由性は上がるが、費用が高くなる |
テント倉庫で使用できる生地の選び方
テント倉庫の性能を左右する重要な要素の一つが「生地」です。
使用する生地は、防火性・耐久性・遮熱性・用途などの要件を満たす必要があり、建築基準法の規制にも影響を受けます。 テント倉庫の生地を選ぶ際には、以下の基準を考慮する必要があります。
・「667号」か「666号」か(建築基準の違い)
・「不燃性物品保管用」か「可燃性物品保管用」か
・「防火地域」「準防火地域」「22条区域」のどこに設置するか
・「延焼のおそれのある部分」か「延焼のおそれのない部分」か
これらの条件によって、使用できる生地の種類が異なります。以下に、代表的なテント倉庫向けの生地を紹介します。
代表的なテント倉庫用生地とその特長
クローザー®V3(ツヤ有りタイプ)
【特徴】
・防火地域でも使用可能な不燃膜材料
・延焼の危険がある場所に対応
・高い耐候性を持つ
【メーカー】
帝人フロンティア株式会社
【種別】
不燃膜材
【材質】
ガラス繊維100%+PVCフィルム
ハリケーン®遮熱
【特徴】
・遮熱性を持ち、省エネ効果が期待できる
・防炎性能を備え、テント倉庫の安全性を向上
・室内温度を下げ、夏場の倉庫内の暑さを軽減
【メーカー】
帝人フロンティア株式会社
【種別】
遮熱膜材・防炎膜材(テント倉庫専用)
【材質】
ポリエステル
エバーマックスUM-200
【特徴】
・200kgクラスの高強度シート
・変退色が少なく、防汚性に優れる
・耐久性が高く、長期間の使用に適している
【メーカー】
平岡織染株式会社
【種別】
防炎膜材(荷捌きテント専用)・高耐久膜材
【材質】
ポリエステル、塩化ビニル
生地の選定に影響する建築基準
テント倉庫の生地は、設置するエリアや用途によって制限されます。以下のポイントを確認しましょう。
① 建築基準(667号 or 666号)
・667号:倉庫・物品保管専用(低コスト・納期短縮向け)
・666号:倉庫だけでなく、作業場・運動施設などの用途にも対応(自由度が高いが費用も上がる)
② 不燃性 or 可燃性の区分
・不燃性物品保管用:陶器・磁石・ガラス・金属・鉄骨など
・可燃性物品保管用:紙・プラスチック・スチロール・木材・布製品など
③ 防火地域・準防火地域・22条区域
テント倉庫の設置場所が、防火地域・準防火地域・22条区域のいずれに該当するかを確認し、適切な生地を選ぶ必要があります。
・防火地域:駅周辺や商業エリア(最も厳しい制限)
・準防火地域:住宅地・工業エリア
・22条区域:防火規制が比較的緩いエリア
④ 延焼のおそれのある部分・ない部分
・延焼のおそれのある部分:隣接する建物や道路に近い部分(より高い防火性能が必要)
・延焼のおそれのない部分:隣接建物から離れた場所(比較的自由な選択が可能)
これらを事前に確認し、長期間安心して使えるテント倉庫を構築しましょう。
テント倉庫の生地を選ぶ際は
テント倉庫の生地を選ぶ際は、設置場所・用途・防火基準を確認し、最適な素材を選定することが重要です。
・不燃性の生地が必要か?
・防火地域の規制に適合しているか?
・耐久性や防汚性を考慮する必要があるか?
これらを事前に確認し、長期間安心して使えるテント倉庫を構築しましょう。
機能別にみる大型テント倉庫の特長
テント倉庫は、用途や設置環境に応じてさまざまな機能を備えています。特に、防水・防火・遮熱・積雪対策などの性能を考慮することで、より安全で快適に使用することが可能です。ここでは、大型テント倉庫を選ぶ際に重要な機能を詳しく解説します。
防水性の高い大型テント倉庫を選ぶポイント
大型テント倉庫は、広いスペースを確保しつつ、雨や風から荷物を守るために設置されることが多いです。特に、防水性・防汚性・耐候性に優れた生地を選ぶことで、長期間にわたり安全かつ快適に利用することができます。
■防水機能のメリット
・雨水の侵入を防ぎ、荷物や設備を保護
・ 雨天時も作業がスムーズに行える(荷物の積み降ろしが可能)
・ 扉を開けても雨水が入りにくい構造を実現
・ 防汚加工により、汚れの付着を軽減
■防水性を高めるための対策
防水性を高めるための対策を3つ紹介していきます。
① 生地の防水加工
テント倉庫の生地は、継ぎ目を防水加工することで、雨水の浸透を防ぎます。また、生地表面にフッ素樹脂コーティングを施すことで、撥水効果と防汚性を向上させ、長期間きれいな状態を保てます。
② 固定庇(ひさし)の設置
庇(ひさし)を取り付けることで、出入り口からの雨水の侵入を防ぎます。また、庇と雨樋を組み合わせることで、豪雨時でも効率よく雨水を排水し、作業スペースを快適に保つことができます。
③ 耐候性に優れた素材を選ぶ
テント倉庫の生地には、屋外での使用に適した耐候性の高い素材を選ぶことが重要です。例えば、UVカット機能を備えた生地を使用することで、紫外線による劣化を防ぎ、長持ちさせることができます。
防火・不燃性能を備えた大型テント倉庫の選び方
大型テント倉庫を安全に運用するためには、火災リスクを最小限に抑えることが重要です。特に、防炎性能や不燃性能を持つ生地を使用することで、火災の発生・延焼を防ぎ、商品や作業員の安全を確保できます。
■防火・不燃性能のメリット
・火の付着による延焼リスクを軽減できる
・自己消火性があり、燃え広がる危険を抑えられる
・防火地域においても設置しやすい
・法規制に適合し、安全基準を満たすことで長期間安心して使用可能
■防炎生地と不燃生地の違い
テント倉庫を選ぶ際、防火性能は非常に重要なポイントになります。
特に、設置する地域や用途によって、防炎生地と不燃生地のどちらを選ぶべきか慎重に判断する必要があります。
| 比較項目 | 防炎生地 | 不燃生地 |
| 燃えにくさ | 燃えにくいが、完全には燃えない | ほぼ燃えない |
| 自己消火性 | あり(火元を離すと自然に消える) | あり(燃焼を防ぐ) |
| 価格 | 低価格で導入しやすい | 高価格だが安全性が高い |
| 用途 | 一般的なテント倉庫 | 防火地域・高い安全性が求められる施設 |
■防炎生地と不燃生地の使い分け
・防火地域では、より高い安全性を確保するため、不燃生地の使用が推奨
→ 消防法や建築基準法に適合し、万が一の火災時にも被害を最小限に抑えられる
・一般地域では、コストを抑えつつ防炎生地を活用
→ 低コストでありながら、基本的な火災対策として機能するため、多くのテント倉庫で使用されている
・火災リスクを抑えることで、商品・設備・作業員の安全を確保!
→ 事前に防火性能を考慮することで、安全な作業環境を維持できる 防炎生地と不燃生地には、それぞれメリットとデメリットがあり、倉庫の設置場所や用途に応じて適切な生地を選ぶことが重要です。
■防火・不燃性能を高めるための対策
火災リスクを低減するための重要な対策を3つ紹介します。
① 防炎生地の選定
テント倉庫で使用される防炎生地は、燃えにくい性質を持ち、自己消火性を備えているのが特徴です。小さな火種が接触しても簡単には燃えず、万が一燃えても延焼を防ぐ性能があります。特に、防炎生地は以下の用途で活用されます。
・一般的なテント倉庫の壁・屋根材
・作業スペースや荷捌き場のカバー
・屋内での使用が想定される倉庫
② 不燃生地の活用
防炎生地よりもさらに高い耐火性能を求める場合、不燃生地の導入が有効です。不燃生地とは、火が付着しても燃えず、燃焼時の有毒ガスの発生を抑える素材を指します。
不燃生地の主な特徴
・建築基準法の不燃材料認定を受けた素材
・高温環境下でも形状を維持できる耐久性
・防火地域・準防火地域での設置義務に対応可能
防火地域や、防炎対策が必須のエリアでは、防炎生地よりも不燃生地を選ぶ方が安全性が高く、長期間安心して使用できます。
③ 防火基準に適合した設置計画
テント倉庫を設置する際は、地域ごとの防火規制を確認し、適切な生地や設計を選択することが重要です。
・防火地域・準防火地域の場合 → 不燃生地を使用し、延焼を防ぐ構造を採用
・一般地域の場合 → 防炎生地での対応が可能だが、可燃物の保管場所に注意
・用途に応じた防火対策 → 消火設備の設置や、可燃性の少ない材料を活用することが望ましい
防火性能の高い倉庫を計画することで、火災リスクを大幅に軽減し、より安全な保管環境を実現できます。
遮熱・断熱機能を備えた大型テント倉庫の選び方
日本の夏は年々気温が上昇し、特に屋外に設置する大型テント倉庫では遮熱・断熱対策が重要になります。適切な遮熱機能を持つ生地を使用することで、倉庫内の温度上昇を抑え、快適な作業環境を確保できます。また、省エネ効果にも貢献し、冷房の効率を高めることが可能です。
■遮熱・断熱機能のメリット
・倉庫内の温度上昇を抑え、作業環境を快適に維持
・省エネ効果が高まり、冷房の負担を軽減
・遮熱効果のある生地を使用することで、紫外線の影響を抑える
・温度変化が少なくなるため、保管する商品や設備の品質を維持しやすい
遮熱・断熱性能を高めるための対策
倉庫内の温度管理を最適化するための重要な対策を3つ紹介します。
① 遮熱シートの効果
遮熱シートは、倉庫内の温度を3~5℃下げることが可能です。
屋根や側面に遮熱シートを使用することで、日射を反射し、熱の吸収を抑える効果があります。
遮熱シートの主な特徴
・赤外線を反射し、直射日光による温度上昇を抑える
・夏場の冷房負荷を減らし、省エネ対策にも貢献
・薄くて軽量なため、テント倉庫にも設置しやすい
遮熱シートを活用することで、猛暑でも快適な作業環境を維持できるようになります。
② 遮熱効果のある生地の選定
テント倉庫で使用される生地には、遮熱性能を持つものと持たないものがあるため、選定が重要です。特に、UVカット加工や特殊コーティングを施した生地を選ぶことで、温度の上昇を抑えることができます。
主な遮熱生地の特徴
・表面に特殊コーティングを施し、熱の吸収を軽減
・透光率を調整し、自然光を取り入れつつ熱を遮断
・高い耐候性を持ち、長期間の使用でも劣化しにくい
適切な生地を選ぶことで、日射の影響を受けにくく、快適な倉庫環境を維持できるようになります。
③ 断熱性を強化した構造設計
倉庫内の温度を一定に保つためには、断熱構造の強化も重要です。特に、以下のポイントを考慮することで、温度変化を最小限に抑えることが可能です。
・二重張りの生地を使用し、熱の伝達を抑える
・側面にも遮熱材を配置し、熱がこもりにくい設計を採用
・換気機能を強化し、倉庫内の熱気をスムーズに排出
遮熱・断熱対策をしっかり行うことで、夏場の温度上昇を防ぎ、冬場も外気の影響を受けにくい環境を作ることができます。
遮熱生地と非遮熱生地の違い
遮熱生地を使用することで、倉庫内の温度上昇を抑え、快適な作業環境を維持できます。一方、非遮熱生地は特に遮熱対策が施されていないため、夏場の直射日光の影響を受けやすく、倉庫内の温度が上昇しやすい特徴があります。
以下の比較表を参考に、それぞれの特性を理解し、用途に適した生地を選びましょう。
| 比較項目 | 遮熱生地 | 非遮熱生地 |
| 温度上昇抑制 | 3~5℃下げる効果あり | 温度上昇を抑える効果なし |
| 省エネ効果 | 冷房の負荷を軽減し、電力コスト削減 | 冷房効率が低下し、電力消費が増える |
| 耐候性 | 紫外線に強く、劣化しにくい | 紫外線による劣化が進みやすい |
| 適用用途 | 夏場の高温対策が必要な倉庫 | 一般的な倉庫 |
■遮熱生地を選ぶべきシチュエーション
・夏場の温度上昇が特に厳しい地域での使用
・冷房設備を導入し、省エネ対策を行いたい倉庫
・食品・化学品・電子部品など、温度変化に敏感な商品を保管する施設
・長期間の使用を想定し、紫外線劣化を抑えたい場合
遮熱生地を使用することで、温度管理がしやすくなり、作業の快適性も向上します。また、長期的に見ても冷房コストの削減に貢献し、電力消費を抑えることが可能です。
■非遮熱生地が適しているケース
・比較的涼しい地域での使用(寒冷地など)
・短期間の使用を前提とした倉庫(イベント会場や臨時施設など)
・遮熱対策よりも初期コストを抑えたい場合
非遮熱生地は、基本的な倉庫用途として使用できますが、夏場の温度上昇や紫外線劣化には十分な対策が必要になります。特に、直射日光が当たりやすいエリアでは、冷房コストが増加する可能性があるため、事前に考慮することが重要です。
雪が多いエリアで大型テント倉庫を安全に使用するためのポイント
積雪の多い地域では、大型テント倉庫の屋根に雪が積もることで、建物の安全性や耐久性に影響を与えることがあります。そのため、雪下ろしの必要がない構造設計や積雪荷重に耐えられる強度の確保が重要になります。
積雪に対応するための設計ポイント
①屋根勾配の工夫
積雪の多い地域では、屋根に雪が積もり続けると構造に負担がかかるため、自然に雪が落ちるような屋根勾配の設計が不可欠です。
屋根勾配を調整するメリット
・積雪の重みを軽減し、骨組みへの負担を抑える
・一定量の積雪で自然に滑り落ちるため、雪下ろし作業が不要
・テント倉庫の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減
屋根勾配は、地域の積雪量に応じた適切な角度で設計することが重要です。
②積雪荷重に耐えられる骨組みの強化
テント倉庫の屋根や骨組みは、地域ごとの最大積雪量に対応できるように強度を確保する必要があります。特に、鋼材のサイズやトラス幅(骨組みの間隔)を適切に設計することで、雪の重みに耐えられる構造を実現できます。
骨組み強化のポイント
・太く強度の高い鋼材を使用し、積雪荷重に耐える
・トラス構造を最適化し、雪の重さを分散
・耐久性の高い布基礎を使用し、地面からの荷重負担を軽減
このように、地域の降雪量に応じた設計を行うことで、雪による影響を最小限に抑えることが可能です。
③出入口や倉庫の配置計画
積雪地域では、落雪時の安全を考慮し、出入口の位置やテント倉庫同士の設置距離を慎重に計画することが重要です。
安全な配置計画のポイント
・落雪が直接影響しないように出入口の向きを調整
・倉庫同士の距離を十分に確保し、雪の落下スペースを作る
・除雪しやすい環境を整え、作業の効率を向上
適切な配置を行うことで、雪による事故を防ぎ、作業効率の低下を防ぐことができます。
■雪が多いエリアでのテント倉庫の適用例
日本国内では、東北地方や日本海側の地域で毎年数メートルの積雪があるため、特別仕様のテント倉庫が求められます。これらの地域では、以下のようなテント倉庫の運用方法が推奨されています。
・高勾配の屋根を採用し、自然落雪を促進
・積雪対応の強化骨組みを導入し、安全性を確保
・耐寒性・耐久性に優れた生地を使用し、長期運用を可能に
まとめ
テント倉庫は、倉庫用途にとどまらず、多様なシーンで活用できる柔軟性の高い施設です。
短期間・低コストで設置できるうえ、防水・防火・遮熱・積雪対策など、環境や用途に応じたカスタマイズも可能です。
導入時には、建築確認申請の要否を確認し、適切な生地を選ぶことで、より安全で長期間にわたり快適に利用できます。倉庫としての活用はもちろん、荷捌き場・スポーツ施設・ショールームなど、新たな活用アイデア次第で可能性は無限大です。
ぜひ、自社のニーズに合ったテント倉庫の導入を検討してみてください!