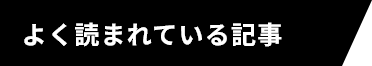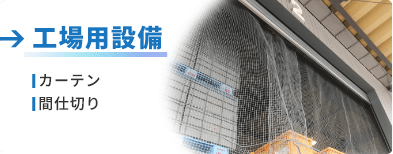工場におすすめの間仕切り・ブース 消防法、耐震性についても解説
 2023.05.20
2023.05.20
 2024.4.19
2024.4.19

間仕切り・ブースのない工場、倉庫は、開放的でいいという方々もいるのかもしれません。
しかし、一方で作業に不都合が出てしまうことはないでしょうか。
間仕切り・ブースを設置することで、
・自由なスペースが生まれる
・外部から入り込むホコリ・虫の侵入を防ぐ
・温度・湿度管理も行うことができる
・電気コストを削減することができる
・安全な環境づくりができる
・整理整頓に貢献する
など様々なメリットを得ることができます。
作業スペース、休憩室、応接室など、間仕切り・ブースを設置することで作業効率も格段とアップするかもしれません。
ただし、消防法の問題、耐震性などあらかじめ留意しておかなければならない注意点もあります。
今回は、工場にどのような間仕切り・ブースがいいか、注意点などをテント倉庫も含めて解説します。
目次
工場にどのような間仕切り・ブースがいい?

間仕切り・ブースがないと、仕事をしている人たちが一目瞭然であるなどのメリットがあります。
しかし、一方では、例えば食品や精密機器を扱っている会社の場合、衛生管理の問題であったり、温度管理の問題など間仕切り・ブースがないことで大きなデメリットになることもあります。
それぞれの工場ではそれぞれの用途に応じ、レイアウトされるべきです。
しかし、大規模な工場のレイアウトを検討することで莫大な費用が要求され、とてもじゃないけど無理という経営者の方々もいらっしゃることでしょう。
間仕切り・ブースという方法であれば、コストも大きく削減することができますし、スピーディーに設置できるためすぐに作業をはじめることができます。
間仕切り・ブースの素材には、アルミであったりスチール、ガラス素材のものがあります。
工場でも、ガラス間仕切り・ブースが光を採り入れることができオシャレでいいと思うかもしれません。
しかし、間仕切り・ブースを設置する上でメリットと同時にデメリットを知り総合的判断をする必要があります。
あえて言えば工場には、アルミやスチール間仕切り・ブースがおすすめ、ガラスの間仕切り・ブースは、衝撃によって割れてしまうリスクがあるためおすすめしません。
アルミの間仕切り・ブース

アルミの間仕切り・ブースは、スチールのものと比較して軽くて設置が楽です。加工もしやすいので短い期間で施工が完了します。
ただし、支柱とパネルのつなぎ目がむき出しになっている出来栄えであるため、オシャレ感はなかなか演出することができないでしょう。
ただし、アルミの間仕切り・ブースでも、パネルのカラーを選択したり、窓ガラスを入れることで見た目は変化させることができます。
また、アルミの間仕切り・ブースは、スチールのものと比較して、防音性や耐震性は低くなります。そのあたりの問題を考慮してケースバイケースで選択するといいでしょう。
スチール間仕切り・ブース
スチールタイプは、遮音性と機密性を維持することができる間仕切り・ブースです。
アルミの間仕切り・ブースと比較して、支柱とパネルのつなぎ目が見えにくいので、経営者の方々もデザイン的にいいものが欲しいという場合には、こちらを選択するといいでしょう。
スチール間仕切り・ブースには、パネルのカラーも豊富にあります。
アルミの間仕切り・ブースと比較し、コストはやや高いですし、期間も長くかかることになりますが、耐震性もあり工場との相性がいいです。
工場に間仕切り・ブース テント倉庫を設置する注意点

工場に間仕切り・ブースならば気軽に設置できるという思いをお持ちの方々が多いことでしょう。
しかし、消防法的問題、耐震性など留意しなければならない点があります。
テント倉庫を設置しようと思っている方々も同じです。
消防法の問題

間仕切り・ブースを作る場合、床から天井までをしっかり区切るものを設置することで、消防法的に、そのスペースがひとつの部屋とみなされることになります。
新しい部屋を設置した場合、消防法の規定では届け出が必要になりますし、消防設備の設置義務が出てきてしまうので要注意です。
間仕切り・ブースは、部屋の新設に該当することがあり、その場合には工事の7日前までに、「防火対象物工事等計画届出書」を消防署へ提出する必要があります。
また、壁や天井材には不燃材を使用する必要があります。
さらに、それぞれ火災報知器と排煙設備を設置する必要があります。
一方で、例えばビニールシートを吊り下げるような簡易な間仕切り・ブースの場合には、部屋という見られ方がしないため、今お話ししたような手続きは必要ありません。
ただしビニールならばいいということでもなく、ビニールでも天井まで覆ってしまうようなケースでは部屋とみなされてしまうため、消防設備の設置が必要であることもあります。
不燃材や防火機能付きの素材を使用する必要性も出てきてしまうことでしょう。
やはり法律的問題は詳しくわからないという方々が多いので、不安・疑問があれば専門業者に問い合わせをする、また消防署へ相談するといいでしょう。
テント倉庫の場合
テント倉庫の場合にも、消防法において不燃物を保管する倉庫の場合の消化設備の配置が必要とされています。
500㎡未満:消火器
500㎡以上:消火器、火災報知器
700㎡以上:消火器、火災報知器、屋内消火栓
耐震性の問題

間仕切り・ブースの設置は、耐震性の問題があり不安という方々は少なくありません。
パーテーション自体、床と天井にパネル、支柱を設置し仕切る役割であるため、どうしても振動に弱いというデメリット要素があります。
少しでもそのような不安を解消したいと思うのなら、「ファクトリブース」の設置を検討するといいでしょう。
ファクトリブースとは、すでに天井の付いた間仕切りで、天井高を気にしないで工場に設置することができます。
ファクトリブースは、広い工場の一角に独立したスペースを作ることができますし、かつ生産に合わせ簡単に移動であったりレイアウトすることができます。
また、他の間仕切り・ブースとは違って、天井付きであるため密閉性が高く、冷暖房をきかせる目的であったり防塵の目的でも使用することができます。
工場の天井が高ければ高いほど工事費は高くなってしまいますし、あまりにも高い場合耐震面の問題で間仕切りだけでは対応出来なくなることがあります。 そのような事態に困っている経営者の方々にファクトリーブースがおすすめです。
テント倉庫の場合

一方でテント倉庫の場合シンプルなメカニズムであるため、耐震性に優れている特徴があります。
基本的に、建物の重さに比例し地震への被害は大きくなると言われています。一般的なテントにおいて鉄材などが使用されますが、テント倉庫で使用している素材は軽い骨組みとテントだけであるため、地震に強くなっています。倉庫自体の重量が軽く、一般的鉄骨建造物より耐震性に優れています。
ただし、テント倉庫の場合は外気にさらされているため、それぞれの工場の環境によって耐用年数にも変化が出てきてしまうことになります。システム工法であったりプレハブ工法と比較しても、テント倉庫の方が短めです。
ただし、ちょっとした工夫によって耐用年数はいくらでも伸ばすことができるものと考えてください。
テント倉庫は、設置する場合の環境に左右されやすい特徴があります。テント生地を紫外線に当ててしまうことで、予想している以上ダメージを受けてしまうことでしょう。潮風の吹く場所に設置することもできるだけ控えた方がいいかもしれません。
そしてよりテント倉庫を長持ちさせたいと思えばメンテする意識も大事です。
台風のシーズンを迎え、雨被害を受けてしまう……ということもあるかもしれません。その時には、即補修しましょう。
テント倉庫には、全面生地張替工事の他にキャッピングという修理の方法があります。
キャッピングとは、生地張り増し工事のことです。テント倉庫の屋根に上から新しい生地をかぶせ固定します。
キャップシート施工なら全体張替えよりも短期間でメンテすることが可能です。全体を張替えるよりも使用する生地や工具も少ないので修繕コストも安く済ませることができます。
まとめ

いかがでしょうか。
今回は、工場にどのような間仕切り・ブースの素材がおすすめか、
消防法、耐震性など注意しなければならないポイントについて解説しました。
作業スペース、休憩室、応接室など、間仕切り・ブースを設置することで作業効率の格段アップを期待することができます。
大規模な工場のレイアウトでは莫大な費用がかかり、とうてい無理……という方々もいらっしゃることでしょう。
間仕切り・ブースであれば、低コストで設置することができます。
工場には、アルミやスチール間仕切り・ブースがおすすめです。
また、テント倉庫もぜひ有効的に活用してみてください。
ただしそのとき検討しなければならないのは、
消防法の問題であり、耐震性、メンテの問題です。
間仕切り・ブースは、どうしても振動に弱いというデメリットがあります。少しでも不安を解消したいなら、ファクトリブースを検討するといいでしょう。
また、台風のシーンを迎えてテント倉庫の全面生地張替工事を検討している方々もいらっしゃることでしょう。テント倉庫の補修には全面生地張替工事以外、キャッピングという方法がありますので検討してください。